3日目10月3日 停滞 風雨強し後半の朝日小屋から出発栂海山荘まで
以前からの天気予報では3日は前線が通過し天気は崩れるとの予報だった。ヤマテンの前日の予報で風雨強いとの予報が確実となったので、今日は停滞を決めたが正解だったようだ。単独行はこのように天気を読んで行程を変更する判断が自分だけで出来るのが良い。又、体の調子により行動を判断する場合もそうだ。昼過ぎて小屋に到着した人は、同室となった男性2人と雪倉岳避難小屋から来たという若い女性一人だったが、ずぶ濡れになりストーブで濡れたものを乾かしていた。翌日の天気予報は、朝雨が残るが日中は晴との予報が出た。
後半篇 海抜0零ZEROを目指して瘠せ尾根 無人の山道を辿る
4日目10月4日 小雨後曇り時々晴れ 行程:朝日小屋~朝日岳~黒岩山~犬ヶ岳~栂海山荘
朝食を済ませ直ぐ出発したが5時40分になった。霧雨が降っているのでパーカーを着て出る。この季節なので雨具にするか迷ったが、ゴアのマウンテンパーカーにしたので少々暑い。標高差200mの登りは何も見えず。ガスの中の頂上。数年前の5月の春スキー以来の頂上だが、全く様子は違う。石造りの丸い山岳案内版横にモニュメントがあったが、四角柱の単純なものに変わっていた。直ぐに出発、白馬岳方面分岐を過ぎかなり下ると吹上のコルに着く。ここから蓮華温泉方面への道と別れ、愈々栂海新道が始まる。岩に赤い大きな字で栂海新道の文字が書かれている。オオシラビソの林を暫く辿ると草原に出るがガスで良く見えない。右に小高い所があるので寄ってみると長栂山の標識があった。なおも下ると漸く明るくなり辺りの景色も広がりパーカーを脱ぐ、アヤメ平の辺りだ。さらに下るにつれ て明るくなり周囲は開け、湿原・池塘が多くなり素晴らしい景観が広がる。斜面は黒岩平に続き今は紅葉と草もみじで色取られているが、夏なら幾多の花が咲き乱れるお花畑だろう。平の向こうには黒岩山が盛り上がり、それに繋がる稜線がはるか遠くに見える犬ヶ岳に続いている。この風景は圧巻だ。


反対側の親不知方から大きな荷物を担いだ若い男性がやってきた。テントを担いで白馬岳に向かっている、挨拶を交わして別れた。黒岩山頂からはこれまで歩いてきた黒岩平が一望に広がり、これから辿る犬ヶ岳への稜線は延々と続いているのも見渡せる。
痩せ尾根を注意しながら下ると「文子の池」の標識のある濁った池がある。ここからアップダウンの激しい稜線が続き、一段と高いピークを登ると「さわがに山」に着いた。そこからもまだ険しいザレた稜線の続きで気が抜けない、こんな所で落ちたら永久に見つからなくて行方不明になること請け合いである。犬ヶ岳の手前に水場がある。北又の水と言い、少し下ると岩の間から水が流れている。2L程必要と、重いのでタンクを入れるポリ袋を探して出かけたが水場手前で袋は持ってきたが、タンクを持ってくるのを忘れていた。

2Lの水が増えてずしりと重くなったザックを背負って犬ヶ岳の頂上に漸く達した。歩いてきた山並が遥かに遠く長く見えた。其の頃から又雨模様となってきたが今日の宿「栂海山荘」までは10分ほどで着いた。この山荘は、土地の山岳会の皆さんの手作りで何年も掛けて徐々に増築したものとのことで、詰めれば50人近く入れる広さになっている。今夜は此処に客人一人だ。貯金箱のような料金箱に2,000円を納めた。その夜は朝日小屋で買った少量のワインを飲み、不味い夕飯を一人で掻き込んだ。毛布がたくさん置いてありそれを借りて片隅に寝床をしつらえて雨の音を聞きながら寝た。
朝日小屋5:40~朝日岳6;45~吹上コル7:15~長栂山8:05~アヤメ平8:35
~黒岩平9:30~10:40黒岩山11:10~文子の池11:40~さわがに山12:30~
犬ヶ岳14:40~栂海山荘14:50
5日目10月5日 曇り時々小雨 行程:栂海山荘~菊石山~白鳥山~坂田峠~親不知海岸
目覚めが遅く4時30分起床、朝飯食べてトイレ済ませ出発が5時40分、又も出発が遅れた。トイレは小屋から50m離れた外れの展望のきく急斜面にパイプで組まれている。真下を見ると汚物が見えてン~感じ。

山荘を出てから直ぐに激しいアップダウンが始まり、下りも捗らない。昔黄連(薬草)を採ったのでこの名がついたという黄連山を越すと綺麗なブナ林になる。ブナ林を過ぎると以前は海底だった証拠のアンモナイトの化石が出た菊石山に着く。化石らしいカケラも見つからなかった。そこから鞍部まで下ると西側が大きく崩壊した下駒ケ岳に取り付き、切り立った岩場になる。岩に取り付き木の根や枝を頼りによじ登る。また鞍部に150m下り200m程急坂を登り返して漸く白鳥山の山頂に着いた。三角点のある狭い山頂、屋根上に見晴らし台のある2階建ての避難小屋が建っている。扉を開き土間に座って休憩した。登山道はほぼ直角に曲がり、ここから標高差700mの急な下降が始まった。途中シキ割という水場を通るが、この辺りは尾根上なのに沢が入り込んだ複雑な地形になっている。ここからまだ300mのきつい急坂が続き疲れて漸く坂田峠にたどり着く。この峠は旧北陸道の一つで、親不知海岸が荒れた時に使われた巻き道だったもので、他にもいくつかのバイパスがあったようだ。

ここまで来るとやっとかなり下りてきた感じになる。少し雨が降ってきて足元がぬかるんできた。峠から尻高山への緩やかな登りとなる。山道も里山風になって楽に歩けるようになったがまだ先は結構長い。道は大きく西に曲がり平たい所が頂上で三角点がある。息を抜いたためか、赤土の道がぬかるんで滑らないように注意していたのに2回ほど滑ってこけて泥だらけになった。踏んだり蹴ったり、一人で頭に来て苦笑い。道は車道の林道と交差しそのまま下ると林間の二本松峠に着き、入道山に登り返す。幾つかのピークを過ぎて海岸に向けて下りが続き、いい加減嫌になった頃に少し殺伐とした杉林を過ぎて漸く登山道入り口に着いた。ザックを置いて80m遊歩道をとぼとぼ下って親不知海岸に出た。暫くすると迎えに来てくれたK君が下りて来た。
GPS軌跡 歩行断面図 沿面距離53km、累積標高差 +4,338m, △6,234m


栂海山荘5:40~黄連山6:30~菊石山7:10~下駒ケ岳8:00~9:20白鳥山9:50~
シキ割10:40~坂田峠11:45~尻高山12:40~二本松峠13:30~親不知登山口14:50

電気化学工業(現・デンカ)の技術者で、青海(青海町、現・糸魚川市)の工場に赴任した小野健が、山々を眺めるうち登山道づくりを志した。部下を誘って「さわがに山岳会」を立ち上げ、町内にかかる犬ヶ岳までという触れ込みで1968年から道づくりを始めた。朝日岳が最終目標であると明かしたのは、犬ヶ岳山頂に達した時だった。手作業で藪を切り開く重労働に加え、富山県側の営林署から国有林盗伐の疑いで摘発されたり、9種の許認可を得るため奔走したりと苦労しながら、1971年夏に全線が開通した。その後、登山者の分散を危惧する富山県朝日町議会が2度にわたり廃道を決議したこともあった。現在は3つの山岳団体が道の補修や草刈りを分担している[1]。2024/11/21 (追加記事)

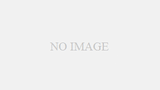
コメント